2013/3/15 7代 新保
先日、「ちょこっとからガッツリへ」と言う7代田畑さんの年間読書量を見て唖然!かなり感化されました!私は家にいるのに、新聞さえ一面と裏のテレビ版くらいしか読まない、活字とは完全にかけ離れた生活をしていたのです。母がホームに入る前は、確か新聞くらいはじっくり読んでいたのに…。何故今は自由な時間があるのにセカセカと一日が過ぎていくのか?全く時間の使い方がおかしい!もったない!
そこで、早速朝30分は読む時間を作るようにしました。珈琲を飲みながら、足は自転車こぎをしながらの「ながら読み」ですが、お蔭様で中々くつろぐ時間になりました。感謝です!
私は就職して暫くしたころ(原紙をガリ版に置いて鉄筆で書いて謄写版で印刷していた時代)、仕事が終わるころになると、目と頭がガンガンして耐えがたくなる日々が続きました。眼科で診てもらうと、乱視の遠視だからメガネを掛けなさいと言われ、それ以来とにかく目が疲れやすくなってしまいました。メガネを掛けない人や目の疲れがない人は本当に羨ましいです。
それでも、松本清張や読みたい物は読んでいたので、40代の頃「飛蚊」と言うものが一気に増え、今では真っ白な壁などを見ると、蚊とは言えないほどの大きな線みたいなものが、うようよ見えて視界を邪魔するようになりました。そんなこんなで「読むことは目が疲れること・飛蚊が増えること」と、インプットされてしまい、さらに目が疲れやすくなったこの頃は、よほど読みたいものがない限り、読書はない生活なのです。
それにしても、新聞まで読まないとはひどすぎますよね!
従って、脳の老化はすさまじく、ちょっと文字を書くと、簡単な漢字も出てこないのは当たり前!先日などテレビ番組の予告で久しぶりに出ていた役者を見て、「あれ~、あの人の名前はなんだっけ~?」「あー、あの女優は誰だっけ~!この前までスラスラ言えてたのに~!」考えても考えても全く出てこないのです。微かな破片も浮かんでこずに日が過ぎて。
母とお昼を食べていたら、突然「あっつ恭兵。柴田恭兵だ!」「もう一人は柴咲コウだ!」2日がかりでやっと出てきました。かなりの重症です!
と言う訳で、疲れない程度に活字と仲良くし、ギターの楽譜を見て、指を動かして、歩いて…、と多面的に脳を鍛えないと大変なことになっちゃうと思いました!(笑)
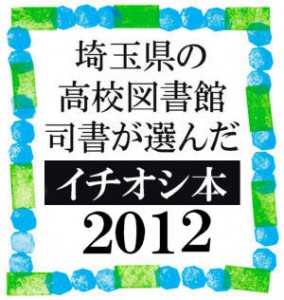 前置きが長くなりましたが、そんな訳で新聞を読んでいたら、高校生向けの推薦図書ベストテンが載っていて、出かけたついでに須原屋を覗くとパンフレットがあったので頂いてきました。超読書家の田畑さんが一番読んでいる「東野圭吾さん」の著書「ナミヤ雑貨店の奇跡」も3位に入っています。既に読んでしまったかもですが…。「何を読もうかな?」と思っている方、万年青春時代の方、若い感覚で読んでみては…いかがでっすか?
前置きが長くなりましたが、そんな訳で新聞を読んでいたら、高校生向けの推薦図書ベストテンが載っていて、出かけたついでに須原屋を覗くとパンフレットがあったので頂いてきました。超読書家の田畑さんが一番読んでいる「東野圭吾さん」の著書「ナミヤ雑貨店の奇跡」も3位に入っています。既に読んでしまったかもですが…。「何を読もうかな?」と思っている方、万年青春時代の方、若い感覚で読んでみては…いかがでっすか?
以下がベスト10です。
第1位 『楽園のカンヴァス』 原田マハ/新潮社
第2位 『ソロモンの偽証』 宮部みゆき/新潮社
第3位 『ナミヤ雑貨店の奇蹟』 東野圭吾/角川書店
第4位 『おもかげ復元師』 笹原留似子/ポプラ社
第5位 『山中伸弥先生に、人生とiPS細胞について聞いてみた』
山中伸弥、緑慎也/講談社
第6位 『旅猫リポート』 有川浩/文藝春秋
第7位 『空飛ぶ広報室』有川浩/幻冬舎
第8位 『きみはいい子』 中脇初枝/ポプラ社
第9位 『夜の国のクーパー』 伊坂幸太郎/東京創元社
第10位
『雪と珊瑚と』 梨木香歩/角川書店
『本日の浮遊』 林ナツミ/青幻舎
本の内容と選者からのコメントは下記リンクをご覧ください。
全受賞作の詳細はここをクリック!
やっぱりちょっと高校生向きかな~?
若者向きみたいですかね!?
私は、今日から朝日新聞に連載が始まった宮部みゆきさんの「荒神」を取りあえず読んでいくことにします。書き出しからなかなか面白そうですよ。でも、明日になって内容を忘れていたらどうしよう!!



暦の上では、このあいだ啓蟄となりましたが、新保さんも本の虫になられたようですね。私の今のおすすめ本は、「和菓子のアン(坂木司著)」、「植物図鑑(有川浩著)」ですね。心が優しくなれます。
目の疲れにはブルーベリーのサプリがおすすめです。私の目はこれで元気になりましたし、夕方になっても疲れを感じることは滅多になくなりました。ファンケルでも売っているので試しに飲んでみて、効果を実感できたら継続すればいいと思います。
あー流石!田畑さん!
パンフレットをコピーして添付するのに時間はかかり、画面は見にくく、
送信しても容量が大きくて戻ってくるはで、四苦八苦いたのですが。。。
リンクとは…!!その手になぜ気づかなかったのか?ガクッ。
きれいな画面で見やすく、内容が詳しく分かるようになりました。
ありがとうっございました。
ブルーベリーはいいと聞くので、サプリは大分飲みました。
今は、冷凍にしたブルーベリーと、アリナミンEXにお世話になっています。
今年も着々と読書が進んでいるようで、何よりですね。
読書ですか。私も興味本位でだらだら読書をします。3月になってから読んだ本の感想を書きます。
癌と末期医療について
近藤誠、中村仁一「どうせ死ぬなら「がん」がいい」(宝島社新書)
近藤誠「医者に殺されない47の心得」(アスコム)
中村仁一「大往生するなら医療とかかわるな」(冬幻社新書)
中村仁一、久坂部羊「思い通りの死に方」(冬幻社新書)
久坂部羊「日本人の死に時」(冬幻社新書)
近藤誠「がん放置療法のすすめ」(文春新書)
私たちもそろそろお年頃です。身近な人の死に接する機会が多くなってきました。養老先生によると、死には三種類あるそうです。
他人の死、身近な人の死、自分の死
です。
以上に関連して
「iPS細胞とは何か、何ができるのか」(日経サイエンス社)
福岡伸一、爆笑問題「生物が生物である理由」
を読みました。生物関係も面白いです。数年前に高校の生物の教科書を読んだこともあります。私たちも生物の1種です。
その他、今月はアルボムッレ・スマナサーラ「ひとりで生きるということ」、隈研吾「建築家走る」、竹内薫「知的生産のための科学的仮説思考」「面白くてねむれなくなる素粒子」、橋口、名越、内田「本当の大人の作法」、鈴木健「なめらかな社会とその敵」
今月は新書が多いですね。編集者もさるもので新書は読みやすくできています。ひとつのテーマにつき10冊ほど読むとアウトラインが見えてくるようにおもいます。田端氏とは読書の傾向が違いますね。私も小説を読みたいのですが、目先の興味に流されて、なかなかたどり着けません。
読書といえるかどうかわかりませんが、スコアも少し読みました。バッハ「マタイ受難曲」を数ページ、マーラー「交響曲1番大1楽章」の最初リピートまで。
昨日は、池袋芸術劇場でマーラーの1番と、シマノフスキーを聴いてきました。