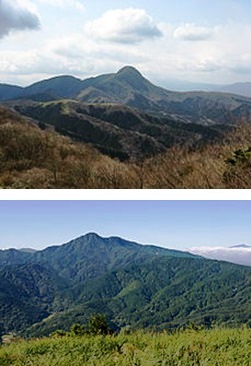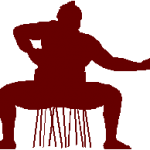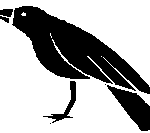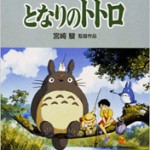ギター仙人
お天気もよく暖かいお出かけ日和の先日、谷根千の街を歩いてきました。「谷根千」というのは谷中・根津・千駄木の略で、たしかこの街のタウン誌の名前だったと思います。今回は、それに文京区弥生まで足を伸ばそうと思っています。
京浜東北線を日暮里駅で山の手側に降ります。まっすぐ行けば「夕やけだんだん」で、その先は谷中銀座ですが、左の道に折れます。すると、駅からわずか5分ほどのところにあるのが、「朝倉彫塑館」です。まず、ここに行くのが今日の目的の一つです。
<朝倉彫塑館>
朝倉彫塑館は、彫刻家朝倉文夫の住居兼アトリエでした。朝倉文夫は、明治16年大分県生まれです。上京して東京美術学校で学んだのち、明治40年にここに住居とアトリエを構えたのです。
大正10年には東京美術学校の教授に就任し、「東洋のロダン」とも称されたほどで、高村光太郎と並んで日本美術界の重鎮となりました。昭和9年に、この自宅兼アトリエを改築して「朝倉彫塑塾」を開き、後進の育成にも力を尽くしました。
朝倉の死後、遺族により朝倉彫塑館として公開されるようになったのは、昭和42年からのことだそうです。
朝倉彫塑館は、長らく保存修復工事をしていましたが、このたびリニューアルして4年半ぶりに開館したのです。
朝倉が自ら設計し、細部にまでこだわって工夫をこらした、和洋折衷の趣のあるつくりになっていて、建物自体が文化財であり、作品であるとも言えます。各部屋を見て回りながら、朝倉の作品と収蔵品を鑑賞することができます。小さな中庭は日本庭園になっており、屋上の庭園は塾だった時の必修科目「園芸」の活動の場でした。

朝倉は猫好きで、多い時は15、6ひきの猫を飼っていたそうです。館内には猫に囲まれてご満悦の彼の写真もあります。猫を題材にした作品も多くありまが、作品についてはホームページで確認してください。朝倉彫塑館

大分県出身の朝倉は、竹田高等小学校で学んだのですが、明治25年に瀧廉太郎と一年間だけ同窓だったことがありました。当時、廉太郎が13歳、朝倉は11歳だったそうです。
その後、廉太郎は「荒城の月」や「花」を作曲し、ドイツにも留学することができましたが、23歳という若さで亡くなってしまいました。朝倉は、同窓だった縁で瀧廉太郎像を作っています。写真の像は大分市のものですが、上野公園の旧奏楽堂前にも朝倉文夫作の「瀧廉太郎像」があります。
谷中は「地域猫」が多く棲む街であり、猫グッズのお店もいくつかあって、街ぐるみで猫を大事にしています。そういう訳で、このあたりは猫好き人が訪れる街にもなっています。
<谷中霊園>
二つ目の目的は、谷中霊園に葬られている歴史的人物に会いに行くことです。ここには、朝倉文夫はもちろん、多くの著名人の墓地があります。一画は寛永寺墓苑にもなっていて、徳川慶喜家の霊廟もあります。
谷中霊園に葬られている人をあげてみれば、植物学者の牧野富太郎、経済界の渋沢栄一、教育者の中村正直、毒婦とされた高橋お傳、横綱の出羽の海、俳優の長谷川一夫、文学者の佐々木信綱、筝曲家の宮城道雄、画家の鏑木清方、横山大観など多士済済です。
洋楽関係でも上真行、島崎赤太郎、本居長世、そして武井守成もここに眠っています。「洋楽事始」に登場してもらった、これらの人々の墓所を確かめるというのが、私の二つ目の目的でした。
念のため、これらの人々について簡単に解説しておきましょう。
上真行(うえさねみち)は、宮内省雅楽所の人で専門は笛だったと思います。音楽取調掛に入学してからは洋楽(ヴァイオリンだったか)を学びました。代表作品は、祝日大祭日唱歌の「一月一日」です。
島崎赤太郎は、東京音楽学校に学んだオルガン奏者です。女性教師陣から権力を取り戻そうとする動き、幸田延の辞職騒動に当時の校長とともに一役かっています。代表作に山形県民歌「最上川」があります。
本居長世は、国学者本居宣長の子孫で、東京音楽学校で山田耕筰と同級生でした。作品には、「赤い靴」「七つの子」など多数の童謡があります。

武井守成は、マンドリン・オーケストラの育成とクラシックギターの発展で大きな功績を残しました。マンドリンのための作品だけでなく、我が国のギター黎明期にその奏法を研究し、オリジナルの独奏曲を残しました。我が国クラシックギター界の最大の恩人です。
武井家は、貴族院議員だった父のときから男爵を授けられていて、敷地も広く大変立派な墓標が造られています。墓標の傍らには、「オルケストラ・シンフォニカ・タケイ」と書かれた右のプレートが作られています。
谷中霊園の墓は、「甲4-5」とか「乙10-9」などと区画と列が表示されているので、表示を目当てに案内図を見ながら歩けばよいのです。あらかじめ場所を調べておけば、それほど探し回らなくても分かるようになっています。
ちなみに「甲4-5」は上真行、「乙10-9」は武井守成の墓のある場所です。そうはいっても、霊園全体が広大なので、上記の人たちの墓所をめぐり歩くと、正味一時間ぐらいかかってしまいました。
谷中霊園の墓めぐりをしている人は、私だけではありません。樹木が豊富で、まあ散歩道としても気持ちよいからでしょうか。案内図を片手にカメラをぶら下げて何やら探し回っている人と何人か出会いました。
また、地元の案内の方に連れられた団体さんもいて、慶喜さんの墓などは、この団体さんに紛れ込んでいると、解説を聞くことができます。
<谷中銀座から根津神社へ>

墓地を後にして、もう一度朝倉彫塑館の前を通り、「夕やけだんだん」を降りて谷中銀座へ向かいました。ここは別に予定していたわけではないのですが、まあぶらぶら歩きながら根津方面に出ようと思いました。
「夕やけだんだん」のあたりには、いつも猫さんたちがいるのですが、今日は日差しが強く、暑いくらいなので物陰に引っ込んでいるのでしょうか。でもいました。大あくびしているのが一匹だけいました。
猫さんに別れを告げて、谷中銀座の通りに入ると、平日だというのにかなりの人出です。どうしてみなさん、こんなに自由な時間があるのでしょうね。まあ、人のことは言えませんが・・・

すると、脇道から自転車に乗った二人の人物が、私の目の前に現れました。なんだか見たことがある人です。どうやらテレビカメラも来ているようで、何かの録画どりをしていたのでしょうか。
狭い道に人がどんどん集まってきて、たちまち大勢の人に囲まれてしまいました。
で、そうならないうちに写真を撮っておきました。たしか、この人たちは俳優の山口智充と佐野史郎という名前だったでしょうか。
彼らがその後どうしたのか知りません。私は、俳優さんとかタレントさんとか芸人さんとかに関心が高い方ではないので、すぐにその場を離れてしまいました。もうお昼をまわってお腹もすいてきましたし・・・
不忍通りに出て根津方面に歩きました。もう、かなり歩いていて上着を脱いでしまうほど気温も上がり、昼は冷たいそばを食べるぞと決めていました。しゃれたお店も多いこのあたりですが、そういうのには目もくれず、下町の普通のおソバやさんに入りました。
ワサビを汁に溶かしこむのではなく、ソバ自体にワサビをつけて、しかしワサビに汁がつかないように、ソバだけを汁につけて啜り込むのが、うまいソバの食べ方なのです。これは、食通で知られた池波正太郎の食べ方ですが・・・。とにかく一休みです。

大通りを渡って、右に行けば根津神社です。創建はヤマトタケルで、1900年も前のことだと伝えられています。
江戸時代この地には、5代将軍綱吉の兄である綱重の屋敷があり、6代将軍家宣の生誕地となったので、徳川家の産土神とされました。
現在は、つつじの名所として知られています。まだ3部咲きですが、すでにつつじ祭りが始まっていて、屋台も並んで大勢の人で賑わっています。
ここは境内を通りぬけるだけにしました。根津神社を出て右に道を登って行くと、左側が東京大学農学部になります。その敷地の手前を入る小道があり、農学部の塀ぞいに進むと、敷地内に入れる扉があり、中には木陰の下を建物まで続く敷石が通っています。扉の傍らに呼び鈴がついていて、その脇に
「レストランにおいでの方は呼び鈴を押してください。お迎えにあがります。」
と書いてあります。どうやら、農学部のレストランがあって、一般の人でも入れるようです。今度来たときには、入ってみようかと思いました。
この先を左折して進むと言問通りに出ます。信号を渡ったところに「弥生土器発掘ゆかりの地」の碑があります。このあたりが文京区弥生町で、明治17年にこの近く(東大の校内)で発掘されたので、その地名をとって「弥生土器」と名づけられたというわけです。
碑と東大の間の道をだらだらと下っていくと、「東大弥生門」の向かい側に「弥生美術館・竹久夢二美術館」があります。ここが、今日の三番目の目的地なのです。
<弥生美術館・竹久夢二美術館>
この私立美術館は、大正・昭和の時代に活躍した挿絵画家の作品が展示されています。
もともとは、画家の高畠華宵(たかばたけかしょう)と親交があった弁護士、鹿野琢見という人物が自宅の一部を美術館にして、華宵の死後、託された作品を展示したものです。現在は、華宵だけでなく明治、大正、昭和の挿絵画家たちの作品が展示されており、その中には、あの「花嫁人形」を作詞した蕗谷虹児も入っています。
また、かつて発行されていいたさまざまな雑誌、「コドモノクニ」「少女画報」「少女倶楽部」「少年倶楽部」など資料的な現物も展示されています。

高畠華宵は、明治21年愛媛県宇和島の生まれです。「少女倶楽部」や「少女画報」などの雑誌に描いた、美少女や美少年の絵や「婦人画報」などの美人画が一世を風靡しました。
大正から昭和にかけては、その独特の画風が人気を集め、竹久夢二と並ぶスター画家としてもてはやされました。
彼は、数多くの美しい少女、女性たちを描き続けましたが、自身は全く浮いた話はなく生涯独身でした。縁談を勧められると
「私には絵の中の女たちはいますから。」
と言ったのというのが、有名な話として残っています。
彼の全盛期に鎌倉の稲村ケ崎に建てた、異国情緒あふれる豪邸は「華宵御殿」と言われ、ここに全国の女性たちから膨大なファンレターが送られたそうです。中には、「華宵御殿」見たさに、家出をした女性まで現れることもあったといいます。
しかし、そうした人気もやがて衰え、戦後は失意の日々を送りました。晩年は生活が困窮して、老人福祉施設に入っていました。
幼少時に華宵の絵が大好きだった弁護士の鹿野琢見が、たまたま華宵の現状を知ることになりました。すると、鹿野は華宵と文通を始め、次第に親交が深めていきました。そして華宵の死後、彼が自宅に弥生美術館が開館したのは、昭和59年のことでした。
平成2年には、弥生美術館に併設して竹久夢二美術館も開館しています。鹿野琢見が収集した夢二の作品が三千点余りあり、こちらではこれを展示しています。夢二の美術館は、岡山、金沢、伊香保などにもありますが、ここの作品群もかなり充実しています。それほど広くないし、訪れる人も多くはないのでゆっくり鑑賞することができました。
入口の右側は、「港や」というカフェになっています。ここで、アイスコーヒーをいただいて一休みしました。美術館に入った人は、100円引きのサービスがあります。
<不忍池から上野へ>

美術館を後にして、東大病院の入口を過ぎたところに稲荷神社があります。かつては、東大側の本郷台地を向ヶ岡、上野公園や谷中の上野台地を忍ヶ岡といい、その境目にこの神社は造られています。
神社の傍らには、「弁慶鏡ヶ井戸」というのがあります。都落ちした義経一行が通りかかったとき、弁慶がこの井戸を見つけて、一行はのどを潤すことができたという記録があることから、この名前がつけられています。
また、昭和20年の東京大空襲のときには、多くの被災者がこの井戸水によって救われたので、現在でも土地の人はこの井戸を大切にしています。

不忍池に出て、左手に池を見ながら遊歩道を歩きます。この遊歩道は今の季節、まことに心地よいところです。たくさんの人がそぞろ歩きをしたり、ベンチに座って鳥たちを見ています。周囲をジョギングしている人もいますし、外国人の方もよく訪れる場所のようです。
やがて弁天堂に出ます。ここを造ったのは天海僧正です。ここは、もともとは中の島だったので、当初は舟で渡ってお参りしたそうです。造営から数十年後に陸つづきなりました。
京都の鬼門を守る比叡山延暦寺に対して、江戸の鬼門にあたる地に東叡山寛永寺を造営した際、不忍池を琵琶湖に見立てたので、竹生島の弁天堂に対する、不忍池の弁天堂が必要になったのです。

ここをねぐらにしている猫たちもいるはずなのですが・・・やっぱりいましたいました。そう、この子に会ったのは何年ぶりでしょうか。ずいぶん年をとったようですが、栄養も足りていて元気そうです。いろんな人の世話になっているのでしょうね。人間に触られても全く平気です。
隠れた目的として、猫さんとの出会いがあったのですが、今回は2匹だけでした。
道路を渡って階段を登り、清水観音堂に出ればもうすぐ上野駅です。東京文化会館の横を通ろうとしたら、一人オーボエを吹いているおじさんがいました。上野公園には大道芸人がいることもありますが、路上で正統派の楽器を演奏している人もよく見かけます。やはり芸大が近いことと関係あるのでしょうか。
上野駅公園口に着いたのは、午後2時52分でした。朝の日暮里駅が9時25分でしたので、約5時間半の散歩となりました。3時前の電車に乗れそうです。