TEA BREAKへようこそ。
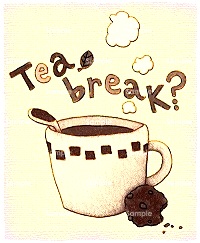
「tea break」とは、ズバリ「お茶の時間」です。
仕事や家事で疲れると一息入れたくなりますね。
そんな時には、お茶を楽しみながら、このページを開けてみましょう。
そこには様々な話題が登場しています。
きっとリフレッシュされて、また活力が湧いて来るでしょう!
記事一覧
- 「Believe(ビリーブ)」
- 洋楽事始 あとがき
- 洋楽事始 第15回 「関係年表」
- 洋楽事始 第14回 「山田耕筰 後編」
- 洋楽事始 第14回 「山田耕筰 中編」
- 洋楽事始 第14回 「山田耕筰 前編」
- 洋楽事始 番外編 その5 文学者と音楽
- 洋楽事始 第13回 「クラシック・ギター 後編」
- 年中行事が消えた。
- 洋楽事始 第13回 「クラシック・ギター 前編」
- 洋楽事始 番外編 その4 キリシタン音楽
- 洋楽事始 第12回 「日本初の音楽評論家」
- 究極のニアピン
- 洋楽事始 第11回 「戦時唱歌と軍歌」
- 洋楽事始 番外編 その3 大山捨松
- 洋楽事始 第10回 「日本初のプロピアニスト 久野 久」
- 洋楽事始 第9回 「日本初のオペラ歌手 三浦 環」
- 洋楽事始 番外編 その2 その後のお雇い外国人
- 洋楽事始 第8回 「瀧 廉太郎 後編」
- 洋楽事始 第8回 「瀧 廉太郎 前編」
- 洋楽事始 番外編の① 漢字で書く楽器名 解答編
- 洋楽事始 番外編の①
- 洋楽事始 「幸田延についての追記」
- 洋楽事始 第7回 「西洋音楽のパイオニア 幸田 延(後編)」
- 稲垣稔 最後のリサイタル
- 洋楽事始 第7回 「芸術音楽のパイオニア 幸田 延(前編)」
- 洋楽事始 第6回 「初めての国産楽器」
- 洋楽事始 第5回 「お雇い外国人」
- 40年ぶりの舞台奮闘記
- 洋楽事始 第4回 「音楽取調御用掛 伊沢修二」
- 洋楽事始 第3回 「女子留学生 永井繁子」
- 洋楽事始 第2回 「サツマバンド」
- 洋楽事始 第1回 「初めて聞く西洋音楽」
- 「童謡」の誕生
- プラス思考の効用
- 「唱歌」の誕生
- 童謡『たきび』について
- バッハからモーツァルトの間
- 『花嫁人形』と蕗谷虹児
- 童謡「赤い靴」の話
- 童謡・唱歌裏話
- ギター界に舞い降りた天使
- 再び、ロジャー・ノリントンの指揮
- パク・キュヒのリサイタルに行って
- トレドな1日
- 談志が、来た。
- ギターの選び方
- OTTAVAを試聴して・・・
- OTTAVAでギターを・・・
- 動じない女(ひと)
- ロジャー・ノリントンの指揮
- 山本直純、耳の逸話
- スペイン語はいかが・・・?
- 我が後輩
- 五感を楽しむコンサート
- 知床旅情
- 山本直純
- 夢と目標について
- ハネムーンとバッハ
- フランシスコ・ベルニエールを聴いてきました。



斉藤さん、「フラメンコの懐かしいレコード紹介」をありがとうございます。文字通り懐かしくもあり、しかし今も息づいている音楽なのだと再確認できました。
さて、斉藤さんがすでに40年も前にフラメンコギターを習っていたことは、その草分け時代の希少価値に対し、驚きとともに敬服してしまいます。内容を読んでいくと、斉藤さんはご自身の中にフラメンコ音楽を蓄えて暖めてきていることがうかがわれ、その感性ある表現に私も入り込んでしまいました。選定された二人はまさに斉藤さんが言うように「フラメンコの伝統的なスタイルを保つ中、あたらしいフラメンコ音楽を築き上げた」巨匠です。
セラニートについては「独自の創造的な音楽の世界を創り出している」こと、「派手さがなく音楽的なコントロールが意図的に働いているように感じられる」、と書いてらっしゃいますが、わたしもセラニートの、あの感情の音の粒が聴く者を包みこむ魔力を感じます。パコについては斉藤さんがブレリアスについて言っているように、「リズムに乗って一音一音正確で歯切れよく、・・・卓越した技法の・・・スピード奏法が、曲の特徴である激しさを盛り上げ支えて・・・」というくだりを読むにつけ、パコのとてもナイロン弦から出される音色とは思えない、太く、時に鋼鉄のような力強い、しかし軽快な音色に魅了された当時がよみがえってきます。
日本では団塊の世代前後の年齢の2巨匠でしょうが、スペインでセゴビアが独奏クラシックギターの地位を築いたように、コンサートフラメンコギターの地位を築いた2人の巨匠を取り上げられたことに共感する次第です。
ところで、セラニートのレコードは私も大好きです。たとえば“ヘレスのフラメンコ”などを思い出しますが、斉藤さんも書いている通り、それこそ「宝石箱をぶちまけたようにこまかい音符で埋められて」いるようで、私も斉藤さんに遅れること約5年ののち、これをはじめて聞いたときはどうやって弾いているのだろう、と繰返し聞いたのを思い出します。
さて、斉藤さんが紹介してくれている、セラニートが使っていたコンサートギターのこと、セラニートに対するセゴビアの感想のこと、などもとても新鮮な驚きをもって読ませていただきました。パコもコンデ兄弟作のクラシック両用風ギターを使っていて同じですし、セゴビアもかつてカンテ・フラメンコの審査員をしたといいますから、そのセラニートへの評価もとても重みがあります。
また、「パコ・デ・ルシアの音楽は、”フュージョン“ということを抜きにしては、語れないように私は感じています」というくだりは、斉藤さんのパコに対する理解の深さがうかがえます。現在ではすっかりこのフュージョンスタイルが定着、さらに発展していることは、パコがコンサートフラメンコギターの地位確立と、もうひとつの一面を世に創出したのだということを再確認させられました。
パコのレコードは私も何度も聞きましたが、どのパッセージのどこを採ってもしっくり行きます。パコはクラシック音楽からもインスピレーションを引き出していたようですし、一族で音楽造りをしているところは、BACH一族と似た境遇なのでしょうか・・・。
セラニートは伝統のニュアンスを最大限にその独創性と最高の技、感性で表現しているのに対し、パコのは表面からは伝統のフラメンコのパッセージをおよそ感じさせない、しかし深いところで感じさせる、二人ともコンパスと伝統を綿々と底面にたたえている、そんなことを感じさせられながら読ませていただきました。
斉藤さんの解説を見て、また2巨匠のレコードを引っ張り出そうと思います。
またシリーズで他のフラメンコギタリストの紹介もいつかお願いできれば幸いです。
10代 佐藤 憲一郎
初めてメールをします。「懐かしいレコード紹介」についての投稿嬉しく思うと同時に興味関心を同じくする同志的な思いもしています。返信が今の時期になってしまったのは、私が最近のコメントの欄を見ていなかったためです。間が抜けた思いがするかもしれませんが、気にしないでいてほしいと思います。私は、最近フラメンコギターの練習を毎日するように心がけています。機会があったら、二重奏でもしてみませんか。とにかく、読んでくれてありがとう。 第5代 斉藤 登