テーマ別投稿
最近のコメント
- ゆるやかな風 第36回 通勤後譚 に 菅田向一 より
- トレド第17回部内発表会報告 に 脇田 美治 より
- トレド第16回部内発表会報告 に 佐藤憲一郎 より
- トレド第15回部内発表会開催! に 佐藤憲一郎 より
- トレド通信 2022年11月号 (活動を再開しています) に 佐藤憲一郎 より
新着記事タイトル
- 2012-12-02: 唱歌・童謡裏話1 みかんと蛙、里の秋
- 2012-11-08: ギター練習ノート 第3回
- 2012-11-05: この1曲~この演奏~この1枚(第8回)村治のアランフェス
- 2012-11-03: 第18回 Leipzig ライプツィヒ (4/4)
- 2012-11-01: 第3回出前演奏会(ゆしまの郷)
- 2012-10-14: ギター界に舞い降りた天使
- 2012-10-01: 第17回 Leipzig ライプツィヒ (3/4)
- 2012-09-21: ギターテレビ放映情報 10月
- 2012-09-18: ギター練習ノート 第2回
- 2012-09-08: 第16回 Leipzig ライプツィヒ (2/4)
記事内容
弦の交換
質問 : 切れそうな弦だけ交換してもよいですか?
4弦の3フレット近くが今にも切れそうになっています。
他の弦は、5弦が少し擦れている以外は問題ないようにみえます。
4弦だけ、あるいは4弦と5弦だけを交換してもよいでしょうか?
それとも最低でも、4~6弦の3本を交換したほうがよいのでしょうか?
昨年10月半ばに、やはり4弦が3フレット近くで切れてしまい、
そのときには6弦全てを交換しました。
ちなみに、練習時間は1週間に3時間程度です。
月に1回のトレド練習日に3時間位弾くので、
平均すると1ヶ月に15~16時間だと思います。
回答よろしくお願いいたします。
黒川です
私の回答:
> ちなみに、練習時間は1週間に3時間程度です。
> 月に1回のトレド練習日に3時間位弾くので、
> 平均すると1ヶ月に15~16時間だと思います。
ということですので、10月からですと別稿での交換の目安50時間にちょうどということで全部交換をお勧めします。
さて、これは大雑把な回答です。
基本的には自分で使えそうと思った弦は交換しなくて良いと思います。
けれどその見分けが付かないでしょう。
4弦5弦が切れやすいので仕方ないのですが、それはそこを使う頻度が高いわけです。
できれば全部の弦を満遍なく使うのが望ましいわけです。
それも全部のフレットにわたって。
*
そこでお勧めなのが
9ポジションの1弦で1,2,3,4と押さえて弾いて、次に2弦で1,2,3,4・3弦で1,2,3,4・・・。
1弦から6弦までやってまた1弦にかえり、ポジションを一つ下げて繰り返し。
という練習をやれば結構その練習だけで満遍なく使えることができます。
*
これにより、楽器自身も音域の中で満遍なく使ってもらえて嬉しいわけです。
楽器も良く鳴るようになるかもしれません。
できれば、できるだけ高いポジションにも挑戦してみましょう。
*
この応用をご紹介します。
これを弾くときに、右手を色々な使い方でやります。
1音ごとに右指を変える弾き方と
1音に付き複数の右指で弾く弾き方があります。
今、はまっている弾き方
*
1音ごとに右指を変える弾きかた:
1弦imam・2弦amim・3弦imam・4弦amim・・・・
これはなれるのに時間がかかるかもしれません。
*
1音ごとに付き複数の右指で弾く
ami・ami・ami・・・・
これはトレモロの練習になります。
*
これは一例で、はじめは自分でやりやすい弾き方で始めるのが良いと思います。
imimimi...でよいと思います。
いきなり難しいのに挑戦するのはかえって良くありません。
工夫してみてください。
*
曲の練習・アルペジオの練習などだと低いポジションの練習が多くなりどうしても3フレット4フレットが切れやすくなります。
上の練習で、できるだけ多くのポジション・多くの弦を使うように意識してみてはいかがでしょうか。
「補遺」
質問の中にもすでにありましたが、低音弦だけ替えるのも良いと思います。
低音弦2回につき、高音弦1回など。
*
チュ―ナ―を用意して1本の弦のいくつかの場所を押さえて弾いてみて、
音の高さが合うかどうかも目安になると思います。
開放弦、7フレット、、9フレット、12フレットなどです。
合うかどうか
これは、自分の楽器の癖もあるので普段からやってみていて、
普段と変わってくるかどうかがポイントかもしれません。
押さえかたでも変わりますから。
**
押弦の力を抜く練習も良いかと思います。
弦・フレットの消耗を少なくするし、何よりも演奏が楽になります。
どこかを押さえます。
右手で弾きます。
左指の力をだんだん抜いていきます。
音がびりつき始めます。
この寸前の力で押さえていれば良いのです。
私はこの左手の脱力が課題となっています。
たくさんのひとの意見がでてくると良いですね。
*
原口さんから
黒川さんの回答でフォローされてますので、若干の追加説明です。
4弦1本だけ新品で、他の弦が古すぎると、
曲を弾いていて4弦の音だけがやや不自然になります。
高音弦はそれほど違いは気になりませんが、
低音弦ははっきりわかります。
そういう時は、4弦だけでなく、
4・5・6弦まとめて交換がベターでしょう。
髪が伸びたので、理髪店や美容院に行った際は、
脇や後ろだけでなく全体をすいてもらうのと同じ理屈ですね。
私は、「理髪」と「弦交換」を同じ気持ちで考えていまして、
一種の気分転換も兼ねています。
弦を交換していい音になると、
気持ちがいいし上手になる気がします。
弦を購入する時ですが、
高音弦1:低音弦2の割合がいいかもしれません。
セット割引にはなりませんが・・
また、低音弦は高音弦の数倍高価なのでムムムですが・・
かつて、生活必需品に比して弦が高価な時代、
当時の教則本には
「低音弦は錆を落として乾燥させて再利用」とありました。
私なんぞ今は1ヶ月使わないうちにゴミ捨てポイですから、
当時のことを考えると妙に感慨深いですね。
また、ギターおたくになりますと、
1弦1弦違うメーカーのものを選ぶ傾向があり、
その場合、セット購入の意味はありません。
さて、黒川さんの半音階導入に1票です。
特に、6弦は普段出番が少ないので、
1弦から6弦を往復するパターンの半音階の練習をお薦めします。
私は、最近、単純スケール練習を減らした分、
左指1324/2343又は3142/4323
のような変形半音階を導入しています。
1弦1フレから6弦12フレまで往復するだけで5分以上かかるので、
私みたいな暇人?でないとフルは無理なので、半分でもいいと思います。
ものはついでに、スラー練習(スラーを~表示)も効果ありますよ。
単純パターンで、1~2/2~3/3~4/3~4/4~3/4~3/3~2/2~1
変形パターンで、2~1/3~2/2~1/4~2又は2~1/3~2/2~1/4~3
こちらは、1~3弦だけでもいいと思います。
尚、薬指・小指が弱い方で部分的に鍛えたい方は、
半音階もしくはスラーで、
3~4/3~4/4~3/4~3
だけを特訓するのも効果的です(最初は苦しくて泣きたくなりますが・・)。
あれれ、いつの間にか、基礎練習の話しになってしまいました。
全部の弦の全部のフレットを使う練習もいいかもということでした。
はぃ。
第7回 緊急リコール
第4代 黒川
第6回の「エクセルで倍音」のワークシートに誤りがありました。
ファイルを訂正してありますので、そちらをお使いください。
新しいファイル名は「baionByExcelv2」(末尾がv2)です。
使ってみていただいた方には申し訳ありません。
お詫び申し上げます。
音を小さくするギターミュート
ギターを弾きたいけれど、音が出るので周囲への気配りが大切です。
特に夜は気をつけないと。
そこで、夜遅く、とかにギターを弾きたいけれど家族や近所への迷惑が心配な方、ワンコインで音を小さくできます。
- GGスーパーギターミュート 630円
- GGミュートくん 525円
詳しくは、現代ギター社のサイトを見てください。
この原理は「ピチカート状態にして音を小さくする」ということです。
実は、あの「近代ギターの父」タルレガも修業時代に、深夜にギターを弾く時は、「タオルをブリッジの近くに巻いて音を小さくした」という逸話があります。(第7代 原口さん情報)
爪の補強、保護 その2 にぼしっ子レポート
食べてみました“にぼしっ子”。
まずは炊き立てご飯にスプーン一杯ふりかけて、と。
む、む、灰色か?薄茶色か?お世辞にも食欲をそそる色とは言えません。
では続けてクンクンと。お行儀悪いですがこれもレポートのため。
おぉー、これは懐かしい丸美屋の“オカカふりかけ”の香り。
子供の頃よくご飯にふりかけたものです。“のりたま”も好きでした。
では、いよいよそのお味は?
パクリ。まさしく、あの“オカカふりかけ”の味そのもの、旨い!
上からちょっとお醤油をかけて、もう一口。
マイブームのキムチものっけて、もう一口。
いやぁ、ご飯がすすんで困りましたー。
さて翌朝、家では朝食はパンとコーヒーであります。
もちろん試してみました、レポートですから。
いつもは、トーストの上にスライスチーズとマヨネーズ、
その上にシソの葉一枚、またはサラダ菜。
そこで、葉っぱをのせる前にスプーンで“にぼしっ子”をパラパラ。
上から葉っぱでフタをして、半分に折ってパクリ。
チーズやマヨネーズの味に隠れてしまうのか、まったく邪魔をしません。
ということで、パン食でもOKです。
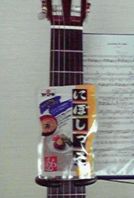
名前から想像していたのは、小魚がザクザク入っている大きな袋。
でも、実物は手のひらサイズの粉末状の商品でした。(70g入り)
(ちなみに価格は、西友ネットスーパーで一袋148円)
ところで、カルシウムって1日にどのくらい摂ればよいのでしたっけ?
数年前に購入した栄養成分事典やサプリメントの本を調べてみました。

“にぼしっ子”は、100gにカルシウムが2000mg含まれます。
量ってみたところ大さじ1杯で約5gでした。これでカルシウム100mgはスゴイ!
体内に吸収される率も考えて多めに摂りたいカルシウム、“にぼしっ子”に頼るところ大ですね。
また、先ほどの本によると、強い皮膚、つややかな髪、健康的な爪をつくるには、たんぱく質の成分として働くイオウが欠かせないそうです。でも、ふだんからたんぱく質を十分に摂っていれば、イオウ不足の心配はないそうですよ。
イオウを多く含む食品は、卵や大豆だそうですから、炊きたてご飯に、“納豆&にぼしっ子&卵”をかけて毎日食べ続ければ、もう恐いもの無し!ですね。
以上、“にぼしっ子”レポートでした。(第7代 榎本)
第6回 ワークシート「エクセルで倍音」の使い方
第4代 黒川
前に書いた記事の中で、ブリッヂの近くを弾くと倍音が多く、遠くを引くと倍音が少なくなる、という意味のことを書いた。それがどのようになっているのか自分でも目でみたくて表計算を使ってやってみることにした。そのワークシートが別掲載されているのでダウンロードして試用してみていただきたい。本稿はその使い方の説明です。 [ファイル:エクセルで倍音(再修正版)]
結果はブリッヂから遠ざかるにつれて高い成分から低い成分にだんだん移行していく様子が見れた。決して倍音が多くなったり少なくなったりではないことがわかった。
それから、倍音に関する一連の記事はあくまで弦だけの振動を簡略化・理想化して見ているもので、
1.胴体その他の影響は考えていない。
2.弦の振動する長さというものは、ナットとブリッヂの距離で決まるのではなく実際の節の
位置はそれよりも少し内側にある。
などということに注意をしていただきたい。たとえそうであっても、ざっとの感じはつかんでおいたほうが良いのではないかというのが考えです。
では、その手法の説明と実際のワークシートの使い方を紹介します。
仮定
1.倍音の節にあたる箇所を弾くと、その倍音の一番小さい音がする。
2.倍音の腹に当たる箇所を弾くと、その倍音の一番大きい音がする。
3.節と腹の中間はそれらの中間で、節に近いと小さく、腹に近いと大きくなる。
目標
1.ある点(ブリッヂの骨棒から何ミリの距離の所)を弾いた時にどんな倍音が出やすいのか。
好みの点の距離を入れると、そこを弾いた時の倍音が色の濃さで出てくる。
そのときの弦長も任意で入力できる。
2.弾く場所をブリッヂに近いところから始めてだんだん遠くしていったら、倍音はどのように
変わっていくのか。一覧で見れるようにする。
このときの弦長も任意で入力できる。
この2種類を今回エクセル上でやってみた。
手法
弦長と弾弦位置(ブリッヂからの距離。[mm])を入力値とする。
弾弦位置が各倍音の腹と節の間のどの位置にあるかを割合で計算する。
結果の表現
腹のときを10。節のときを0。として0から10の数字で表現した。
0から10を4段階の色の濃さで表した。
8から10:一番濃い
4から8:中間
2から4:薄い
0から2:白色(着色なし)
使い方
ワークシートが3枚あります。
1枚づつ説明します。
1.1箇所を弾いた場合
自分の楽器の弦長を入力する。
ここを弾いたらどうなるのか知りたい場所の位置を入力する。
この2箇所を入力すると、すぐに倍音の強さが色分けされて表示される。
2.弾弦位置が等間隔
弦長を入力するだけで、40mmから200mmまで弾弦位置を10mm間隔で計算します。
パターン状に観察できます。
3.弾弦位置が倍音の腹
弦長を入力するだけで、弾弦位置が倍音の腹にあたる位置を弾いた場合を計算します。
パターン状に観察できます。
以上です。使い方は易しいと思いますので、是非試してみてください。
第5回 弦
第4代 黒川
原口さんと田畑さんが、別稿で弦の選び方というのをこのホームページに載せている。この中で原口さんが交換の目安は50時間と言われている。時々気にしてはいて、どの位かなと思っていたことに具体的数字が出てきたので自分を振り返ってみた。今、週末しか楽器を手にすることは無く、弾いているのは週末の二日合わせて4時間くらいだろうか。そして、弦は大体3ヶ月で交換している。3ヶ月で13週間とするとまさに52時間で替えている。学生時代は1日8時間で週1回替えていたからこれも56時間。50時間というのはまことに目安となる数字だなあと感心した次第。
で、前から弦の交換はもったいないと考えているけれどもこればかりはしようが無い。音程が狂う・音の伸びがなくなる・きれいな音が出なくなるなど我慢しきれなくなって替えてしまう。毎週替えていた時などは張ってからすぐに弾き出すので、調弦を繰り返しながら落ち着かせる。その間弾いている。このために、フレットでこすれた跡が長くついて余計にダメージを与えていた。
最近弾く頻度が少なくなってから良いことに気がついた。それは、張ってから約1週間は弾かずに、ただ調弦だけは毎日しておくと「持ち」が良いということ。例えば日曜日の夜に張って、金曜の夜までは調弦だけして他は我慢する。そして土曜の朝やおら弾き始める。するとなぜかその後の「持ち」が良い。良い音の期間が長くなる。1週間弾かないと我慢できない人にはお勧めできないけれども、そうでない人には是非お勧めしたい。
弦がパッケージに入っているときの巻き癖をとるために張る前の弦を窓辺につるしている人がいるときいたことがある。軽いおもりを1本1本につけて、上から吊っていたそうだ。何日か吊っておいてから張る。巻き癖というのは大きく巻いている(目に見える)癖と、目に見えないがねじれの方向の癖も必ずあるはずだ。
弦が振動するときのことを想像すると、その動きは平面の上で動いているとつい思ってしまう。蛇がその体を地面から離さずに体をくねらせているように。しかし実際はそういうことは少なく(ほとんど無い?)立体的に振動している。つまり、縄の両端を二人の子供が持ってまわしてその中にもう一人の子供が入って跳ぶ縄跳びの縄のような動きもあるということ。また、あるところで、「弦を弾くときに弦を回す感覚を持つこと」という指導の言葉を見たことがある。これは弦自身がその断面円の中心を中心にして回動する動き(指先で弦を転がす・ねじれ)と、先の縄のような動きとのどちらかはわからない。わからないけれども、そういうことを考えるとパッケージでの巻き癖を取るというのは大事なことかしらんと思う。思うけれどもまだ確かめていない。


